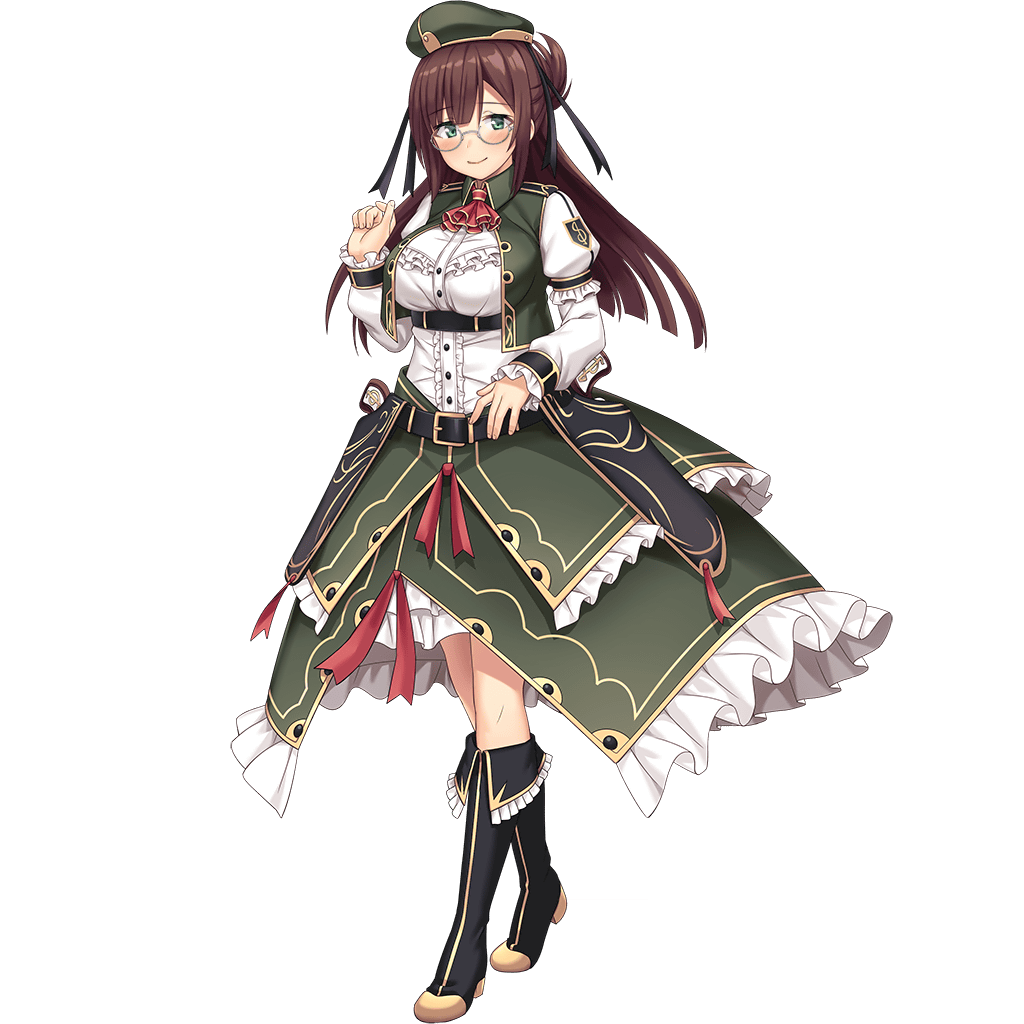|
モデルとなった人物はロシアの作曲家である
ドミートリイ・ドミートリエヴィチ・ショスタコーヴィチ(1906/09/25-1975/08/09)。
キリル文字表記ではДмитрий Дмитриевич Шостакович。
生没年からわかる通り、ソヴィエト政権下での活動がその生涯の大半を占める作曲家である。
多くの交響曲を書き、室内楽曲、協奏曲、オペラにバレエ音楽、歌曲、映画音楽にも佳曲を遺しているが、いわゆる宗教音楽の類はカバーしていない。
労働歌「インテルナチオナール」のオーケストラ編曲などもおこなった。
こんにちの「ソヴィエト連邦の体制により意に沿わない作曲活動を強いられた悲劇の作曲家」としてのショスタコーヴィチのイメージは、
『ショスタコーヴィチの証言』(以下、『証言』とする)によるものであろう。
『証言』については内容に疑問の余地が多く、偽書とする向きもあるが、参考資料の一として、
あるいは単にショスタコーヴィチという人物に思いを馳せる一種の「触媒」として利用するにはいいだろう。
ちなみにこの『証言』にはショスタコーヴィチの恩師であるグラズノフや、プロコフィエフ、ストラヴィンスキーなども登場する。
【経歴】
以下、主にwikipediaと『証言』をもとに年表を再構成した
1906年9月25日
ロシア帝国の首都であるサンクトペテルブルクに生まれる。
1915年
はじめて両親に伴われてリムスキー=コルサコフの「サルタン王の物語」を鑑賞。
同年、母親からピアノのレッスンを受け、作曲を始める。
シドルフスカヤ商業学校に入学する(9歳)。
1916年
グリャッセール音楽学校に入学する(10歳)。
1917年
政情不安・社会不安のなか、路上で警察官が同年代の少年を殺害するのを目撃し衝撃を受ける。
グリャッセール音楽学校への通学を断念(10歳)。
1917-1918年
ローザノヴァにピアノを習う。
1919年
ペテルブルク音楽院に入学しグラズノフに師事する(13歳)。
グラズノフは学生の面倒見がよく、経済的に苦しかったショスタコーヴィチに目をかけていたようだ(『証言』ほかによる)。
1922年
父が死去(15-16歳)。
1923年
音楽院ピアノ科を修了。
結核療養のためクリミアを訪れ、同地にてピアノ・リサイタルを開く(16-17歳)。
1925年
音楽院作曲科を修了し、音楽院を卒業。
修了作品は「交響曲第一番」であった(18-19歳)。
1926年
音楽院の研究課程に進む(19-20歳)。
1927年
第一回ショパン国際ピアノコンクールに出場し入選(20-21歳)。
ちなみに第一位はダヴィッド・オイストラフの伴奏などで有名なレフ・オボーリンであった。
1930年
バレエ音楽「黄金時代」を作曲し、初演するも失敗(23-24歳)。
1931年
バレエ音楽「ボルト」を作曲し、初演するも失敗(24-25歳)。
1932年
ニーナ・ヴァルザルと結婚。
婚約記念として書いていた歌劇「ムツェンスク郡のマクベス夫人」を献呈。
作曲家同盟レニングラード支部の運営委員に選出(25-26歳)。
1933年
ピアノ協奏曲第一番の初演(26-27歳)。
1936年
プラウダ批判を受ける。長女が生まれる(29-30歳)。
1937年
レニングラード音楽院の講師となる。
交響曲第五番「革命」を初演し成功(30-31歳)。
1938年
長男が生まれる(31-32歳)。
1939年
ムソルグスキー生誕100年記念祭の準備委員会委員長となる。
レニングラード音楽院の教授に就任(32-33歳)。
1940年
労働赤旗勲章受章。ピアノ五重奏曲がスターリン賞を受賞(33-34歳)。
1941年
交響曲第7番「レニングラード」を作曲。
レニングラード音楽院の教授を辞任(34-35歳)。
1943年
モスクワ音楽院教授に就任(36-37歳)。
1946年
レーニン勲章受章(39-40歳)。
1947年
レニングラード音楽院教授に復職。
ロシア共和国人民芸術家の称号を得る。
ロシア共和国最高議会代議員に選出(40-41歳)。
1948年
ジダーノフ批判をうけ両音楽院の教授職を解かれる(41-42歳)。
ヴァイオリン協奏曲第1番などを作曲するが、ジダーノフ批判の手前公表を控えた。
この時期の一部作品は1953年、スターリンの死後に発表。
1949年
オラトリオ「森の歌」を作曲し初演(42-43歳)。
1950年
「森の歌」がスターリン賞第1席を受賞。
ソヴィエト平和擁護委員会委員となる(43-44歳)。
1953年
スターリンの死。
交響曲第10番作曲、初演。
内容の暗さなどを巡って大論争が起こる(46-47歳)。
1955年
母の死(48-49歳)。
1956年
レーニン勲章を再び受賞(49-50歳)。
1958年
右手の麻痺(脊椎性小児まひ)で入院(51-52歳)。
1961年
ソビエト共産党党員になる。
レニングラード音楽院大学院での教職復帰(54-55歳)。
1962年
交響曲第13番を作曲、初演。
ソヴィエト連邦最高会議代議員に選出。
右手の治療のため三度入院。
イリーナ・スピーンスカヤと再婚(55-56歳)。
1965年
心臓病の増悪により入院。
ソヴィエト芸術学名誉博士の学位を得る(58-59歳)。
1966年
自身の生誕60年記念演奏会出演。
心筋梗塞で入院。
レーニン勲章をまたまた受章。
社会主義労働英雄の称号を受ける(59-60歳)。
1969年
交響曲第14番を作曲、初演(62-63歳)。
1971年
二度目の心筋梗塞で入院。
10月革命勲章を受章(64-65歳)。
1973年
姉の死(66-67歳)。
1975年
フランス芸術アカデミー名誉会員となる。
絶筆となった「ヴィオラソナタOp.147」を完成させ、7月に入院。
8月4日再入院ののち、モスクワの病院にて8月9日、没(68歳)。
死因は肺がんであった。
【人物】
ショスタコーヴィチはその生涯において度々病を患っている。
結核や小児まひ、心臓病に肺がんなどである。
病弱キャラといえるかもしれないが、病気がちな一方、かなりのサッカー好きで、趣味が高じて審判資格も持っていた。
作曲した作品の傾向を概観すると、前衛的な作品が目立つ初期作品群にはじまり、
体制の要求によるいわゆる「社会主義リアリズム」的な作品を書いた中期の作品、
ユダヤ系の音楽などの引用やスターリンの死後に顕著になる前衛的作風の復活、
晩年の独自の透明な作品世界へと移り変わる。
政治的な要求に応えざるを得なかった時代を除けば、ショスタコーヴィチの作品の底流にあるのは前衛性と、
自らの病などに端を発したであろう死への思いなどであったといえよう。
(以下、補足)
ちなみに頭書にて語ったとおり、こんにちショスタコーヴィチは「体制の要求する音楽を書く葛藤に苦しんだ」作曲家であるとされがちであるが、
『証言』の出版以前には「体制に迎合したプロパガンダ作曲家」であるとの見方が大勢を占めており、
決してショスタコーヴィチという人物が西側諸国において好意的に扱われることは多くなかった。
1975年という比較的近い時代に亡くなった人物の伝記について、その真贋を巡る論争があることには意外とされる向きもあるかもしれない。
しかし『証言』の内容は同僚であった音楽家たちへの辛辣な批判や、ソヴィエト体制に対する異議申し立てなどが多く含まれており、
これはつまり反社会主義体制的な立場(たとえば英米などの国々)からすれば逆プロパガンダとしての意味を持っていたことになる。
近現代を生きた人びとにとっても、彼らの描かれた生涯は大いに時流の影響により時に歪められ、誇張されてしまうものなのである。
(補足ここまで)
【ショスタコーヴィチとムラヴィンスキー】
エフゲニー・ムラヴィンスキーは、ショスタコーヴィチと熱い友情によって結ばれた指揮者であった。
交響曲第5番「革命」の初演の後、交響曲では第6、8、9、10、12番、オラトリオの「森の歌」、
またヴァイオリン協奏曲第1番をダヴィッド・オイストラフと、チェロ協奏曲第1番をムスティスラフ・ロストロポーヴィチとそれぞれ初演した。
ショスタコーヴィチの交響曲第8番はムラヴィンスキーに献呈された交響曲であるが、
第二次世界大戦のさなか作曲され、その戦争の惨禍と犠牲者への追悼の念の籠った同曲は、
ソヴィエト連邦作曲家同盟をはじめ国内の同業者への受けも悪く、またジダーノフ批判の対象ともなって1960年まで演奏が禁止された。
粛清の虞さえあったショスタコーヴィチを救ったのは、ムラヴィンスキーその人であった。
批判され、その立場を危うくしていたショスタコーヴィチの交響曲第5番を積極的に演奏会プログラムに取り入れ、
同曲への深い共感と理解に基づく指揮で以て聴衆を感動させることで、ショスタコーヴィチの音楽を認めさせたのである。
そんなムラヴィンスキーだが、ショスタコーヴィチの交響曲の全曲録音は遺していない。
録音があるのは第5、6、7、8、10、11、12、15番に限られるが、いずれも素晴らしい内容である。
なお、ムラヴィンスキー自身はあまりに多くの逸話のある巨匠指揮者である。
彼の紹介を本格的に始めると何冊かの本になってしまいかねないので、興味を持たれた指揮者様はどうぞ、彼に纏わる本などをご一読めされては。
| ![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/title-logo1.png)
![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/title-logo1.png)