![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/title-logo1.png)
セシル・フランク †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 進化後_ |
| 超進化後_ |
| プロフィール | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
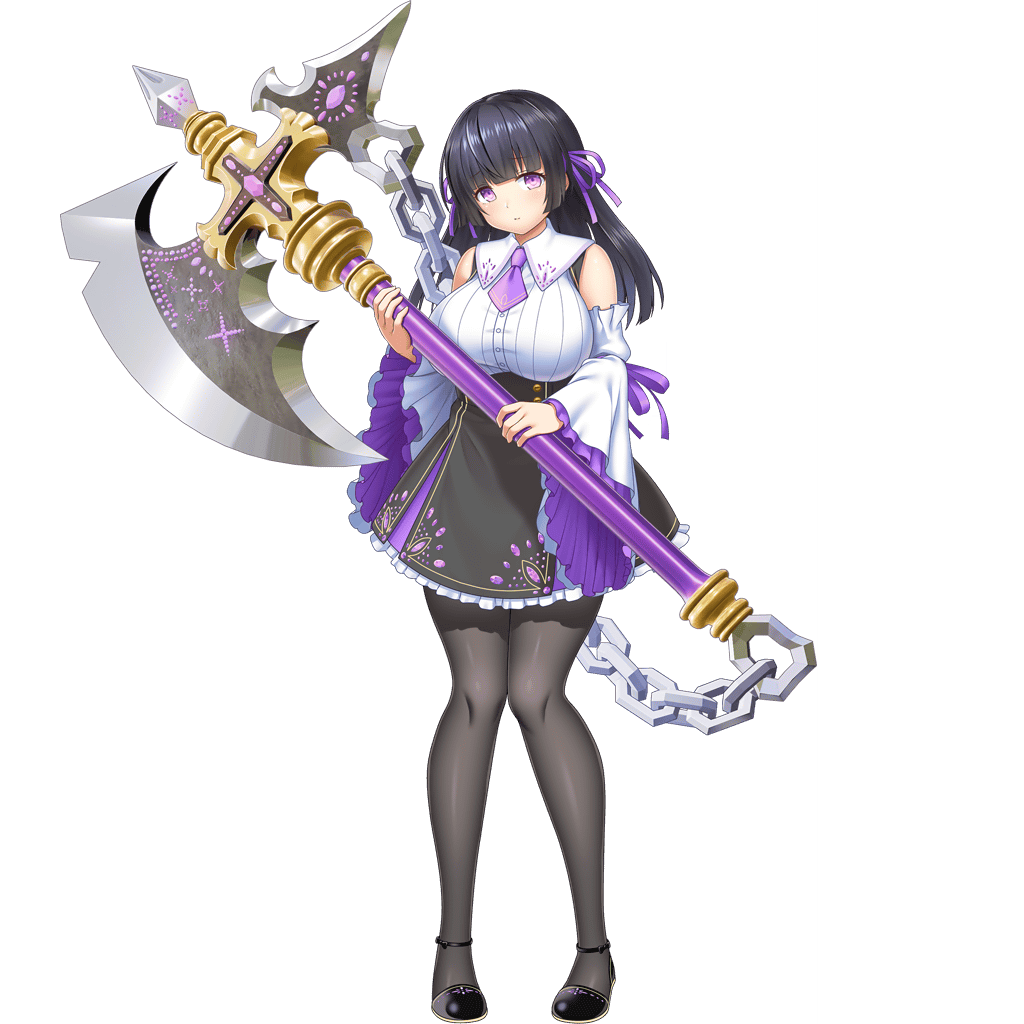 は、初めまして……セシル・フランクといいます。 お、大きいですか? やっぱり大きいですよね……すみません。 あの、身体は大きいですけど、 ちゃんと楽器は弾けますから…… オルガンとか、ヴァイオリンとか得意です。 で、でも、みんなほど上手じゃないと思うので…… その、コンダクターさんが望むなら、 弾除けにでも使ってくれたら……と、思います。 | 名前 | セシル・フランク | ||||
| レアリティ | ★★★★ | |||||
| 属性 | 荘厳 | |||||
| 武器種 | 斬 | |||||
| 種別 | 演奏家 | |||||
| 出身 | シャルロワ地方 | |||||
| 好きな物 | ワッフル | |||||
| 特技 | 精密作業 | |||||
| 趣味 | ビーズアート | |||||
| 長所 | 真面目で真摯/小さいことからコツコツと | |||||
| 夢 | いつか自分よりも大きい人が お姫様抱っこしてくれること | |||||
| SD | キャラクターアニメGIFを添付 演奏会アニメGIFを添付 | |||||
| パラメータ | ||||||
| LV90 | 生命力 | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 演奏力 | ゲージ速度 |
| 11819 | 10228 | 12251 | 9274 | 13092 | 100 | |
| 攻撃耐性 | 演奏耐性 | クリティカル発生率 | ダメージ増加率 | ガード発生率 | ダメージカット | |
| 100% | 200% | 20% | 100% | 100% | 349 | |
| スキル | ||||||
| 特殊攻撃 | 交響的大曲 | Lv極 | 30%の確率で、186%のダメージ&演奏力を11%UP | |||
| 音楽魔法 | 3つのコラール | Lv11 | 敵1体に1200%のダメージ&自身の演奏力を25%UP | |||
| 戦闘スキルアニメGIFを添付 | ||||||
| アビリティ | ||||||
| アビリティ:1 | 大きくてすみません | 第1楽章 | 被ダメージ時、一定確率で自身の防御力を6%UP | |||
| 第2楽章 | 被ダメージ時、一定確率で自身の防御力を8%UP | |||||
| 第3楽章 | 被ダメージ時、一定確率で自身の防御力を10%UP | |||||
| アビリティ:2 | 12度を掴む手 | 第1楽章 | 攻撃時、一定確率で自身のダメージカットを5%UP | |||
| 第2楽章 | 攻撃時、一定確率で自身のダメージカットを7%UP | |||||
| 第3楽章 | 攻撃時、一定確率で自身のダメージカットを8%UP | |||||
| シンフォニア装備 | ||||||
| デコラティブアクス | Lv60:防御力+747 演奏力+1743 | フランクが持つシンフォニア装備。 重量感ある巨斧に宝石の装飾が施されている。 ときには身を護る楯にもなる頼れる武器。 | ||||
| ★★★★★上限解放 |
2021年3月5日開始のイベント電子の海に浮かぶ音の報酬として実装された☆4の楽団員。
| 元ネタ解説_ |
| ボイス_ |
| 表情差分_ |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照